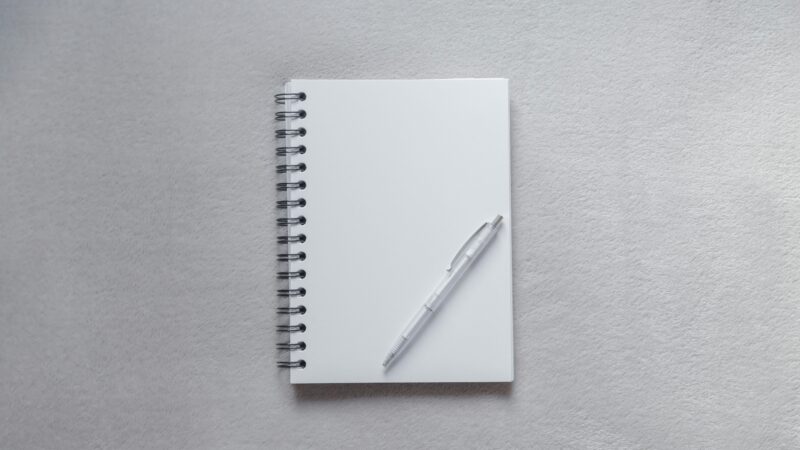マーケティングの「手法」は、もう学ばなくていい。成功の設計図は、驚くほどシンプル。

私たちの周りには、常に「マーケティング」という言葉が漂っています。
テレビCM、スマートフォンの広告、街中の看板。
ビジネスの世界に足を踏み入れようとするとき、あるいは日々の消費活動の中でさえ、この言葉はまるで空気のように存在しています。
しかし、その実態を正確に捉えている人は、どれほどいるでしょうか?
マーケティングとは、特定の分析手法の名前だろうか?
それとも、商品を巧みに宣伝する技術のことだろうか?
あるいは、複雑な専門用語の集合体なのだろうか?
多くの人が、マーケティングを断片的な知識や、どこか掴みどころのないイメージで捉えているかもしれません。まるで深い霧の中を手探りで進むように。
この記事は、その霧を晴らすために存在します。
マーケティングの本質とは何か。そして、あなたがビジネスで、あるいは人生で何かを生み出そうとするとき、本当に理解しておくべきことは何なのか。
小手先のテクニックや、流行り廃りのある手法ではありません。
時代が変わっても揺るがない、原理原則。
それを、誰にでもわかる言葉で、順を追って解き明かしていきます。
複雑に見える世界も、本質を捉えれば驚くほどシンプルに見えてくるはずです。
さあ、マーケティングの核心へと、一緒に旅を始めましょう。
誤解だらけの「マーケティング」 – その本質は、たった一つの言葉に集約される
「マーケティングって、結局何なの?」
この問いに、あなたは即座に答えられるでしょうか。
多くの人が、メディアミックス、SWOT分析、4P分析、あるいは著名な学者の名前を思い浮かべるかもしれません。しかし、それらはマーケティングという広大な領域の一部に過ぎません。枝葉の部分です。
では、その根幹、本質は何なのでしょうか?
驚くほどシンプルです。
マーケティングの本質とは、突き詰めれば、
売上を上げること
ただ、これだけです。
しかし、これだけでは十分ではありません。9割の説明にしかならない。
なぜなら、「売上を上げる」という結果だけを見ていては、そのプロセスを見失ってしまうからです。
真の本質は、そのプロセスにあります。
売上を上げるための「流れ」を作ること
これが、マーケティングの全てを要約する言葉です。
商品やサービスが、それを必要とする人の手に自然と渡っていく。その一連の道筋、仕組みを設計し、構築すること。それこそがマーケティングなのです。
考えてみてください。
あなたが明日、500万人が視聴する情報番組で、自分の商品を宣伝する機会を得たとします。これは大きなチャンスです。
このチャンスを最大限に活かし、最も効率的に「売上を上げる流れ」を作るには、どうすれば良いでしょうか?
- タレントに商品を使ってもらい、感想を放送する?
確かに、一時的な注目は集まるかもしれません。多くの人が「試してみたい」と思うでしょう。しかし、その熱狂は持続するでしょうか?3ヶ月後、半年後、1年後も売上は上がり続けるでしょうか? - 視聴者に「検索してください」「LINEに登録してください」と呼びかける?
興味を持った人をリスト化し、継続的な関係を築く。これも一つの有効な手段です。
何が最適解かは、状況によって異なります。
しかし、重要なのは、単発の施策ではなく、継続的な「流れ」を意識することです。
テレビCM一つをとっても、その場で商品を売るだけでなく、
- 興味喚起: 「面白そう」「自分に関係ありそうだ」と思わせる。
- 情報提供: 商品の詳細や利点を伝える。
- 行動喚起: 検索、問い合わせ、購入へと促す。
- 関係構築: 購入後も繋がり、次の行動(リピート、口コミ)へと繋げる。
このような一連の流れを設計することが、マーケティングの核心なのです。
メディア露出、SNS運用、広告出稿、メールマーケティング、資料請求……世の中には様々なマーケティング手法が存在しますが、それらは全て、この「売上を上げるための流れ」を作るための手段に過ぎません。
まずはこの大原則を、しっかりと心に刻んでください。
マーケティングとは、「流れ」を作ること。そのために、様々な道具(手法)があるのだ、と。
真のマーケターを見抜く視点 – 営業ができない者は、語る資格がない?
「売上を上げるための流れを作る」
それがマーケティングの本質であると理解した上で、次に考えるべきは、「誰がその流れを上手く作れるのか?」ということです。
世の中には、「私は優秀なマーケターです」と自称する人がたくさんいます。ウェブマーケティングの専門家、様々な実績を持つコンサルタント……。しかし、その言葉を鵜呑みにしてはいけません。
真に優秀なマーケターと、そうでない者を見分ける、決定的な指標が一つあります。
それは、極めてシンプルでありながら、本質を突いています。
その人物は、「営業」ができるか?
なぜ、マーケターに営業力が求められるのでしょうか?
一見、関係ないように思えるかもしれません。しかし、深く考えれば、その繋がりは明らかです。
マーケティングとは、「商品やサービスが顧客の手に渡るまでの道筋を作る」ことでした。
この道筋を作るためには、顧客の気持ちを理解することが不可欠です。
- 顧客は何に悩み、何を求めているのか?
- どんな言葉に心を動かされ、どんな情報に関心を持つのか?
- 購入を決断する際には、どんな不安や疑問を感じるのか?
これらの顧客心理を理解せずして、効果的な道筋(流れ)を作ることなど不可能です。
想像してみてください。
あなたがラーメン店を開くとします。顧客がどんな味を好み、どんな体験を求めているかを知らずに、「俺の考えた最強のラーメンだ!食え!」と独りよがりな商品を提供したら、どうなるでしょうか?
- 豚骨好きな人に、ハーブたっぷりの創作ラーメンを出す。
- あっさり味を求める人に、濃厚ギトギトラーメンを出す。
これでは、顧客は満足しません。リピートにも繋がりません。
営業という行為は、まさにこの顧客理解が試される最前線です。
売れる営業担当者は、必ず顧客の気持ちを深く理解しています。
- 相手の言葉に耳を傾け、真のニーズを引き出す。
- 相手の状況や感情に寄り添い、最適な提案を行う。
- 相手の不安を取り除き、信頼関係を築く。
つまり、営業ができるということは、顧客の心を読み解き、動かす力があるということの証明なのです。
であるならば、マーケティングと営業は表裏一体であると言えます。
マーケティングとは、営業をより簡単に、より効率的にするための仕組み作り
こう捉えることもできるでしょう。
例えば、「セールスレター」と呼ばれる縦長のウェブページがあります。通販サイトなどでよく見かける形式です。
あれは、まさに営業の流れを1枚のページに凝縮したものです。
- 問題提起: 「あなたはこんなことで悩んでいませんか?」
- 共感: 「その気持ち、よくわかります」
- 原因分析: 「悩みの原因は、実はこれなんです」
- 解決策提示: 「そこで、この商品が役立ちます」
- 証拠提示: 「実際に使った人の声です」「専門家も推奨しています」
- 行動喚起: 「今すぐ手に入れて、悩みを解決しましょう」
このように、顧客の心理ステップに沿って情報が配置され、自然と購入へと導くように設計されています。これもまた、営業の流れをマーケティングの形に落とし込んだ例です。
結論として、営業ができないマーケターの話は、信用に値しません。
顧客の気持ちがわからない人に、売れる流れを作ることなどできないからです。
真のマーケターは、必ず営業の本質を理解し、実践できる力を持っています。
優秀なマーケターの、残りの二つの鍵
営業力(顧客理解力)が最も重要であることは間違いありません。全体の8割を占めると言っても過言ではないでしょう。しかし、真に優秀なマーケターには、あと二つの重要な能力が備わっています。
- ストーリー作り マーケティングは「流れ」を作ることだと述べました。この「流れ」は、言い換えれば「ストーリー」です。
顧客が商品やサービスに出会い、興味を持ち、購入し、そして満足して口コミを広げる……この一連の体験は、一つの物語として捉えることができます。- ラーメン店の看板を見て、入店を決意するまでのストーリー。
- メニューを見て、注文するまでのストーリー。
- ラーメンを味わい、会計を済ませ、店を出るまでのストーリー。
- 満足して、友人に勧めたり、SNSで共有したりするストーリー。
優秀なマーケターは、顧客の心を動かす魅力的なストーリーを設計し、語ることができます。 - プロジェクトマネジメント(PM) どんなに素晴らしいストーリー(戦略)を描いても、それを形にできなければ意味がありません。計画を実行に移し、管理していく能力。それがプロジェクトマネジメントです。
- チラシを配布した、広告を出した、SNSで投稿した……しかし、思ったような反応が得られない。どう改善すればいいか?
- 他の企業や個人と協力して何かを進めようとしたが、人間関係が上手くいかず、計画が頓挫しそうだ。どう軌道修正すればいいか?
優秀なマーケターは、これらの問題を乗り越え、計画を最後まで遂行するための管理能力を持っています。- 広告効果の測定と改善
- 予算の管理
- 人的リソースの調整
- 関係者とのコミュニケーション
- ストーリー全体の進捗管理
戦略を立てるのが得意なマーケターは多くいます。しかし、その戦略を現実に落とし込み、結果を出すところまで責任を持てるマーケターは稀です。
営業力(顧客理解)、ストーリー作り、プロジェクトマネジメント。
この三つの要素が揃って初めて、真に優秀なマーケターと言えるのです。
全ての始まり – ゴールはどこにある?
マーケティングの全体像と、優秀なマーケターの条件が見えてきました。
では、実際に「売上を上げる流れ」を作るために、私たちはまず何から始めるべきなのでしょうか?
戦略、戦術、ストーリー……考えるべきことはたくさんありますが、その全ての出発点となる、たった一つの重要なことがあります。
それは、「ゴール設定」です。
なぜゴール設定がそれほど重要なのでしょうか?
例を挙げて考えてみましょう。
あなたが、友人を集めてパーティーを主催するとします。
このパーティーの「ゴール」を、どう設定しますか?
- ゴールA: 「可愛い女の子とお金持ちの男性を引き合わせる」
- ゴールB: 「参加者同士が連絡先を交換する」
どちらのゴールを設定するかで、パーティーの企画内容、運営方法、そして参加者の満足度は大きく変わってきます。
ゴールAの場合、見た目の華やかさや表面的な出会いを重視するかもしれません。しかし、内気な人やコミュニケーションが苦手な人は、輪に入れずに終わってしまう可能性があります。「良い出会いはなかった」と感じる人もいるでしょう。
一方、ゴールBの場合、参加者同士が自然と交流し、繋がりを持てるような仕掛けを考えるはずです。名札に趣味を書いたり、簡単なゲームを取り入れたりするかもしれません。たとえその場でカップルが成立しなくても、「新しい人と話せて楽しかった」「連絡先を交換できた」という満足感を得られる可能性が高まります。
このように、ゴール設定が、取るべき行動と得られる結果を方向づけるのです。
マーケティングにおいても、これは全く同じです。
何かを始めるとき、必ず「目的(ゴール)」を明確にしなければなりません。
そして、このゴールを設定する上で、絶対に忘れてはならない視点があります。
顧客は、最終的に何を求めているのか?
多くのマーケターが陥る罠は、「商品を買ってもらうこと」をゴールにしてしまうことです。しかし、これは間違いです。
考えてみてください。
ラーメンを買った顧客は、ラーメンそのものが欲しいわけではありません。
「美味しいラーメンを食べて満足したい」「空腹を満たしたい」という目的があるはずです。
もしラーメンがまずかったら、たとえ購入という行動は完了しても、顧客の目的は達成されず、二度と来店しないでしょう。
逆に、もしあなたが「世界一まずいラーメン専門店」を開いたとします。(極端な例ですが)
そして、「まずいラーメンを体験したい」という好奇心旺盛な顧客が来店し、期待通り(?)まずいラーメンを食べたとします。この場合、顧客の目的は達成され、ある種の満足感を得るかもしれません。
つまり、重要なのは商品そのものではなく、顧客がその商品やサービスを通じて達成したい「目的」なのです。
顧客の満足とは、非常にシンプルな原理に基づいています。
顧客が期待していたこと = 実際に得られた体験
この方程式が成り立ったとき、顧客は満足します。
「ここに来てよかった」「この商品を買ってよかった」と感じるのです。
ですから、マーケティングの第一歩は、「顧客が真に求めている目的は何か?」を深く理解し、それを明確なゴールとして設定することから始まります。
自分たちの商品やサービスが、顧客のどんな目的達成に貢献できるのか?
そこを徹底的に考え抜くことが、全ての戦略の基礎となるのです。
ビジネスを動かす4つの歯車 – 最も重要なのは、どこか?
顧客の目的を理解し、ゴールを設定しました。
次はそのゴールに向かって、具体的な「流れ」を作っていく段階です。
ビジネスというシステムは、大きく分けて4つの要素(歯車)で構成されていると考えることができます。
あなたがどんな種類のビジネスを行うにしても、この4つの要素は必ず存在し、それぞれが連動して機能しています。
- 集客: あなたの商品やサービスに興味を持つ可能性のある人々を集める活動。
- 販売: 集めた人々に商品やサービスを購入してもらうための活動。営業やセールスプロセス。
- 商品(サービス): 顧客に提供する価値そのもの。
- 運営管理: ビジネスを持続させるための活動全般。予算管理、人材管理、方向性の決定など。
この4つの歯車の中で、最も重要なのはどれだと思いますか?
多くの人は、「商品(サービス)」と答えるかもしれません。「良いものを作れば売れるはずだ」と。
あるいは、「販売」力こそが鍵だと考える人もいるでしょう。
しかし、マーケティングの観点から見ると、圧倒的に重要なのは「集客」です。
なぜでしょうか?
考えてみてください。
どんなに素晴らしい商品を作っても、どんなに巧みな販売トークを用意しても、そもそも顧客がいなければ、何も始まりません。
レストランに誰も来なければ、どんな絶品料理も提供できません。ウェブサイトに誰も訪れなければ、どんな魅力的な商品も売れません。
集客こそが、ビジネスの全ての源流なのです。
なぜ「商品」よりも「集客」が優先されるのか? – パッケージという名の第一印象
「いや、やっぱり商品が良ければ、自然と人は集まるはずだ」
そう反論したくなるかもしれません。特に、長年ビジネスに携わっている人や、自分の作るものに自信を持っている人は、そう考えがちです。
「うちの商品はこんなに素晴らしいのに、なぜ売れないんだ?もっと広く知ってもらえれば、絶対に売れるのに」
という相談を受けることは、非常によくあります。
しかし、残念ながら、「良い商品=売れる」という図式は、現代においては必ずしも成り立ちません。
もちろん、商品やサービスの質が低いよりは高い方が良いに決まっています。質が高ければ、リピーターが増えたり、良い口コミが生まれたりする可能性は高まります。
しかし、人々が最初に商品を選ぶ(購入を決める)理由は、必ずしもその「中身」ではないのです。
想像してください。
あなたがパスタを食べたいとします。目の前に二つの選択肢があります。
- A: 美しいお皿に、彩り豊かに盛り付けられたパスタ。
- B: シェフが手づかみで「はい、どうぞ」と差し出す、お皿にも乗っていないパスタ。(味はAと同じだとします)
あなたはどちらを選びますか?
おそらく、ほとんどの人がAを選ぶでしょう。
これは極端な例ですが、重要な示唆を含んでいます。
人は、商品の中身を吟味する前に、「見た目」で判断しているということです。
言い換えれば、
人は「パッケージ」で商品を買っている
のです。
- 美味しそうな料理の写真
- 洗練された商品のデザイン
- 魅力的なキャッチコピー
- 信頼できそうなウェブサイトの雰囲気
- 好感度の高い店員の接客
これら全てが「パッケージ」であり、顧客の第一印象を形成します。
中身を試す前に、「これは良さそうだ」「これは自分に合っていそうだ」と感じさせる力。それがパッケージの力です。
最近、コンビニエンスストアで売られているペットボトル飲料の形が変わってきていることに気づいたでしょうか?
以前よりも細長い形状のものが増えています。
これは、行動経済学の研究で「細長い形状のボトルは、通常の形状のものよりも高級に見える」という人間の心理傾向が分かっているためです。
中身が同じでも、パッケージ(ボトルの形)を変えるだけで、より高級な印象を与え、購買意欲を高めることができる。これもパッケージ戦略の一例です。
もちろん、パッケージだけが良くて中身が伴わなければ、リピートには繋がりません。
しかし、最初の「出会い」の段階では、パッケージ(印象)が決定的な役割を果たすのです。
ですから、マーケティングで最初に注力すべきは、「いかに魅力的なパッケージを作るか」ということになります。
どうすれば、顧客の注意を引き、興味を持ってもらい、「試してみたい」と思わせることができるか?
この「印象作り」こそが、集客の第一歩なのです。
集客第一主義 – 新規とリピートの両輪
集客が最も重要である、と述べました。
ここで言う「集客」には、二つの側面があります。
- 新規顧客の獲得: まだあなたの商品やサービスを知らない人を、新たに見込み客として集めること。
- リピート顧客の維持・促進: 一度購入してくれた顧客との関係を維持し、再購入や口コミを促すこと。
この二つは、車の両輪のようなものです。どちらか一方だけでは、ビジネスは上手く回りません。
- 新規顧客がいなければ、ビジネスは先細りします。
- リピート顧客がいなければ、常に新規顧客を獲得し続けなければならず、コストがかさみます。
マーケティング戦略を考える際には、常にこの両方の視点を持つことが重要です。
- 新規顧客向け: 魅力的なパッケージ(第一印象)で注意を引き、興味を持ってもらう。
- リピート顧客向け: 質の高い商品・サービスで満足度を高め、継続的な関係を築くためのコミュニケーションを行う。
「集客第一主義」という考え方は、この両方を包含します。
常に「どうすればもっと人を集められるか?」という問いを持つこと。
それが、新規顧客の獲得とリピート顧客の維持、両方の戦略へと繋がっていくのです。
ビジネスの4つの歯車(集客、販売、商品、運営管理)の中で、まずは「集客」に最大限の意識を向けること。
それが、マーケティングの最も基本的かつ重要な原則です。
売上を構成する3つのドライバー – あなたは何を伸ばすべきか?
集客の重要性を理解したところで、次に「売上」そのものが、どのように構成されているのかを見ていきましょう。
企業の売上、あるいはあなたのビジネスの売上は、突き詰めると、たった3つの要素の掛け算で決まります。
この3つの要素を理解し、それぞれを向上させていくことが、売上アップの鍵となります。
マーケティングの世界では、売上を上げるために、以下の3つの要素を伸ばしていくことが基本とされています。
- 新規顧客数: 新たにあなたの商品やサービスを購入してくれる人の数。
- 顧客単価: 顧客一人あたりが、一回の購入で支払う金額。
- 購入頻度(リピート率): 顧客が、一定期間内に再度購入してくれる回数や確率。
売上 = 新規顧客数 × 顧客単価 × 購入頻度
このシンプルな方程式が、全てのビジネスの売上構造を表しています。
つまり、売上を伸ばすためには、
- より多くの新規顧客を集める
- 顧客一人あたりの購入金額を上げる
- 顧客にもっと頻繁に購入してもらう(リピーターを増やす)
このいずれか、あるいは複数を改善していけば良い、ということになります。
先ほど解説した「ビジネスの4つの歯車」と、この「売上を構成する3つのドライバー」は、密接に関連しています。
- 集客 → 新規顧客数の増加、購入頻度の向上(リピーター維持)に直接貢献
- 販売 → 顧客単価の向上(アップセル、クロスセル)、新規顧客数の増加(成約率向上)に貢献
- 商品(サービス) → 購入頻度の向上(リピーター化)、顧客単価の向上(高付加価値化)に貢献
- 運営管理 → 上記全ての活動を支え、効率化する
例えば、
- 魅力的なパッケージ(集客)で新規顧客を集め、
- 質の高い商品(商品)で満足度を高めてリピーターにし(購入頻度アップ)、
- 関連商品を提案する販売(販売)テクニックで顧客単価を上げる。
このように、4つの歯車を上手く回すことで、売上を構成する3つのドライバーが向上し、結果として全体の売上が伸びていくのです。
マーケティング戦略を立てる際には、常にこの「新規顧客数」「顧客単価」「購入頻度」という3つの指標を意識し、「今、自分たちのビジネスはどの要素を伸ばすべきか?」「そのために、4つの歯車のどこを改善すべきか?」と考えていくことが重要です。
古典にして基本 – DRM(ダイレクトレスポンスマーケティング)の構造と限界
さて、マーケティングの基本的な考え方、ビジネスの構造、そして売上を構成する要素が見えてきました。
ここからは、具体的なマーケティング手法の世界に少し足を踏み入れてみましょう。
数あるマーケティング手法の中でも、特に基本中の基本として、長年多くのビジネスで活用されてきた考え方があります。
それが、「ダイレクトレスポンスマーケティング(DRM)」と呼ばれるものです。
あなたも、知らず知らずのうちに、このDRMに基づいたアプローチに触れているはずです。
例えば、
- デパ地下の試食販売
- サプリメントの無料お試しや低価格モニター
- メールマガジンの登録
- LINE公式アカウントへの友だち追加
これらは全て、DRMの考え方を応用したものです。
DRMの基本的な構造は、逆三角形のモデルで表されます。
見込み客(多くの人々)
↓ 興味・関心
リスト(連絡先を知っている人々)
↓ 教育・信頼構築
顧客(低価格商品・お試し購入者)
↓ 関係深化
優良顧客(中・高価格商品購入者、リピーター)DRMの核心は、「いきなり商品を売ろうとしない」という点にあります。
顧客との関係性を、ステップを踏んで徐々に深めていくアプローチを取ります。
恋愛に例えると分かりやすいかもしれません。
街で素敵な人に出会ったとします。その人に、いきなり「付き合ってください」「結婚してください」と迫ったら、どうなるでしょうか?
おそらく、成功する確率は極めて低いでしょう。
通常は、
- 興味を持ってもらう: まずは相手に自分を知ってもらい、関心を持ってもらう。
- 連絡先交換: 会話を通じて打ち解け、連絡先(LINE、Instagramなど)を交換する。
- 関係構築: メッセージのやり取りやデートを重ね、お互いを理解し、信頼関係を築く。
- 告白・交際: 十分に関係が深まった段階で、想いを伝え、交際に至る。
DRMも、これと非常によく似たプロセスを辿ります。
- リスト獲得(興味喚起):
まず、あなたの商品やサービスに興味を持つ可能性のある人を集めます。無料サンプル、お試し価格、役立つ情報提供などを通じて、「ちょっと試してみようかな」「もっと知りたいな」と思わせ、メールアドレスやLINEなどの連絡先(リスト)を獲得します。デパ地下の試食は、まさにこの段階です。 - 教育(信頼構築):
リストを獲得したら、すぐに商品を売り込むのではなく、顧客との関係性を築き、信頼を得るためのステップに入ります。これをDRMでは「教育」と呼びます。
メールマガジンで役立つ情報を届けたり、LINEで親近感のあるメッセージを送ったり、商品の魅力や開発ストーリーを伝えたりすることで、「この人(会社)は信頼できそうだ」「この商品は自分に合っていそうだ」と感じてもらうのです。
試食販売のおばちゃんが、「このソーセージ、美味しいでしょ? 実はね……」と商品のこだわりを語りかけるのも、一種の教育と言えます。 - 販売:
十分に信頼関係が築かれ、顧客の購買意欲が高まったタイミングで、商品の購入を提案します。最初は比較的購入しやすい低価格帯の商品から始め、徐々に中価格帯、高価格帯の商品へと繋げていくこともあります。
この「リスト獲得 → 教育 → 販売」というステップを踏むことで、いきなり商品を売り込むよりも、はるかに高い確率で顧客を獲得し、長期的な関係を築くことができる。これがDRMの基本的な考え方です。
現代におけるDRMの課題 – なぜリストは力を失うのか?
このDRMは、長年にわたり非常に効果的な手法とされてきました。
しかし、現代においては、この古典的なDRMだけでは、かつてほどの効果を発揮しにくくなっています。
「見込み客リストを集めているのに、なかなか商品が売れない」
「メールを送っても、LINEを送っても、反応が薄い」
もしあなたがマーケティングに関わっているなら、このような悩みを抱えているかもしれません。
なぜ、DRMの効果は薄れてきているのでしょうか?
理由はいくつか考えられますが、主な要因は以下の2つです。
- ライバルの増加:
DRMの手法が広く知られるようになり、多くの企業や個人が同じようなアプローチ(無料オファー、メルマガ、LINE登録など)を行うようになりました。その結果、顧客は日々大量のオファーに晒され、一つ一つに注意を払うことが難しくなっています。「またこのパターンか」と、見慣れてしまっているのです。 - 情報過多:
インターネットとスマートフォンの普及により、私たちはかつてないほど大量の情報にアクセスできるようになりました。商品を購入する前に、レビューサイトをチェックしたり、SNSで評判を検索したり、複数の選択肢を比較検討したりすることが当たり前になっています。
一つの情報源(例えば、登録したメルマガ)だけで、すぐに購入を決断する人は減っています。あちこちの情報を参照し、納得するまで時間をかける傾向が強まっています。
これらの要因が複合的に作用した結果、「リスト毀損」と呼ばれる現象が起きています。
つまり、せっかく集めた見込み客リスト(メールアドレスやLINE)が、時間とともに反応しなくなってしまうのです。
- メールを開封しなくなる
- LINEをブロックする
- 登録したこと自体を忘れてしまう
どんなに多くのリストを集めても、それが「生きたリスト」でなければ、売上には繋がりません。
現代のマーケティングでは、単にリストを集めるだけでなく、集めたリストとの関係性をいかに維持し、活性化させていくかが、より重要な課題となっているのです。
忘れさせない技術 – 顧客を「回遊」させるということ
リストを集めても、顧客はあなたのことを簡単に忘れてしまう。
情報が溢れ、ライバルも多い現代において、これは避けられない現実です。
では、どうすれば良いのでしょうか?
どうすれば、顧客との繋がりを保ち、忘れられない存在であり続けられるのでしょうか?
その答えは、「回遊」という考え方にあります。
まるでマグロが広大な海を泳ぎ続けるように、顧客をあなたの周りで、常にぐるぐると泳がせ続けるのです。
一度リストに登録してもらったら、それで終わりではありません。
その顧客が、普段から利用している様々な場所(プラットフォーム)で、あなたの情報に繰り返し触れる機会を作る必要があります。
思い出してもらうための仕掛け
これが、現代マーケティングにおける「回遊」の鍵です。
なぜ、人はお気に入りの商品や、かつて熱中したものでさえ、忘れてしまうのでしょうか?
もちろん、「飽きたから」「もっと良いものを見つけたから」という理由もあるでしょう。
しかし、最も根本的な理由は、
人は、単純に「忘れる」生き物だから
です。
あなたのクローゼットの中を見てみてください。
昔、とても気に入って買ったのに、最近全く着ていない服はありませんか?
本棚には、感動して読んだはずなのに、内容をほとんど思い出せない本はありませんか?
人間の記憶は、常に新しい情報によって上書きされていきます。
どんなに強い印象を受けたものでも、時間が経ち、他の情報に触れ続けるうちに、記憶の奥底へと沈んでいってしまうのです。
これは、ビジネスにおいても全く同じです。
顧客は、あなたの商品のことを、あなたが思っている以上に簡単に忘れてしまいます。
だからこそ、定期的に「思い出させる」作業が必要不可欠なのです。
顧客が普段、どこで情報を得て、何に時間を費やしているか?
そこに、あなたの存在を示す「接点」を設けることが重要になります。
そのための有効なツールが、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)やPR(パブリック・リレーションズ)です。
- SNS (YouTube, X (旧Twitter), Instagram, Facebook, TikTok, etc.):
多くの人が日常的に利用しているSNSは、顧客との継続的な接点を作る上で非常に強力なツールです。役立つ情報、面白いコンテンツ、親近感の湧く投稿などを通じて、常に顧客の視界に入り続けることができます。 - PR (テレビ、雑誌、ウェブメディアなど):
メディア露出は、広範囲な認知度を獲得し、信頼性を高める効果があります。特にテレビなどのマスメディアの影響力は依然として大きく、ブランドイメージの向上にも繋がります。
多くの人は、SNSを「新規顧客を集めるためのツール」と考えがちです。もちろん、その側面も重要ですが、それだけではありません。
SNSは、「既存顧客や見込み客に、自分たちのことを忘れさせないためのツール」としても、極めて有効なのです。
考えてみてください。
メールアドレスやLINEだけに頼っていると、顧客がメールを開かなくなったり、LINEをブロックしたりすれば、関係は途絶えてしまいます。
しかし、顧客が普段から使っている複数のSNSで繋がっていれば、どこか一つの接点が途切れても、他の接点で関係を維持することができます。
回遊戦略のポイント:
- リスト登録者を他のSNSへ誘導する: メール登録者にはXアカウントを、LINE登録者にはYouTubeチャンネルを案内するなど、複数の接点を持つように促す。
- 各SNSで継続的に情報を発信する: 顧客がどのプラットフォームにいても、あなた(のビジネス)の情報に触れられる状態を作る。
- プラットフォームに合わせた情報発信: 各SNSの特性やユーザー層に合わせて、発信する内容や形式を最適化する。
このように、顧客を様々なプラットフォーム間で「回遊」させることで、忘れられるリスクを減らし、常に顧客の意識の中に存在し続けることができます。
これが、情報過多時代のマーケティングにおいて、極めて重要な戦略となるのです。
もしあなたが今、SNSを活用していないのであれば、それは大きな機会損失かもしれません。
大企業のように莫大な広告費をかけられない中小企業や個人事業主にとって、SNSは顧客との関係を維持し、忘れられない存在となるための、最も身近で効果的なツールの一つと言えるでしょう。
マーケティングの核心 – 5つの創造(メイキング)
ここまで、マーケティングの基本的な考え方、ビジネスの構造、DRMとその現代的な課題、そして「回遊」の重要性について解説してきました。
これらは、マーケティングを理解する上で非常に重要な要素です。
しかし、これらはどちらかというと、個別の手法や考え方に焦点を当てたものでした。
では、より大局的な視点で、マーケティング戦略全体を捉えるには、どうすれば良いのでしょうか?
私がもし、ゼロからビジネスを立ち上げる、あるいは既存のビジネスを成長させるためのマーケティング戦略を考えるとしたら、必ず5つのステップ(あるいは構成要素)から思考を始めます。
私はこれを「5つのメイキング(創造)」と呼んでいます。
この5つのメイキングこそが、マーケティング戦略の本質であり、王道であると考えています。
- コンセプトメイキング(Concept Making): 魅力的な「概念」を創造する
- コンテンツメイキング(Content Making): 価値ある「中身」を創造する
- リストメイキング(List Making): 継続的な「関係性」を創造する
- メディアメイキング(Media Making): 広範な「認知」を創造する
- ルールメイキング(Rule Making): 有利な「環境」を創造する
この5つのメイキングを順に考え、実行していくことで、再現性の高い、効果的なマーケティング戦略を構築することができます。
ここからは、それぞれのメイキングについて、より詳しく見ていきましょう。(特に、最初の3つは初心者にとって極めて重要です)
1. コンセプトメイキング: 勝てる土俵の見つけ方
全てのビジネスは、「コンセプト」から始まります。
コンセプトとは、その商品やサービスが「何であるか」を一言で表す核となる考え方、あるいは「どのような価値を提供するのか」という約束です。
前半で述べた「パッケージ戦略」は、まさにこのコンセプトメイキングの一部と言えます。
顧客に対して、どのような印象を与え、どのような期待を抱かせるか。それを設計するのがコンセプトメイキングです。
あなたがパン屋さんを開きたいとします。
しかし、世の中には既に無数のパン屋さんが存在します。大手チェーンから、こだわりの個人店まで。
この競争の激しい市場で、単に「美味しいパンを作ります」というだけでは、顧客に選ばれるのは難しいでしょう。なぜなら、他の多くのパン屋さんも同じことを言っているからです。
ライバルと同じことを言っていては、埋もれてしまうだけです。
だからこそ、「勝てるコンセプト」を見つけ出す必要があります。
どうすれば、ライバルとの違いを明確にし、顧客にとって魅力的な存在となれるか?
そのために、まず考えなければならないのは、以下の2つの要素です。
- 市場: あなたが参入しようとしている市場(パン市場)には、どれくらいの顧客がいて、彼らは何を求めているのか?
- ライバル: その市場には、どれくらいの競合がいて、彼らはどのようなコンセプトで戦っているのか?
市場の大きさと、ライバルの数・質によって、取るべき戦略は全く異なります。
- ブルーオーシャン(ライバルが少ない市場):
もし、顧客はたくさん求めているのに、提供しているライバルがほとんどいない、という状況(ブルーオーシャン)を見つけられれば、比較的シンプルなコンセプトでも成功する可能性があります。「この地域で唯一の〇〇パン専門店」といった打ち出し方です。 - レッドオーシャン(ライバルが多い市場):
しかし、現代のほとんどの市場は、ライバルがひしめき合うレッドオーシャンです。パン市場もその典型でしょう。このような状況で勝つためには、他社との明確な差別化が不可欠です。
レッドオーシャンで勝つための、最もシンプルかつ効果的な戦略。
それは、「専門性」を打ち出すことです。
何か一つに、徹底的に「絞り込む」
「美味しいパン」という曖昧なコンセプトではなく、特定の何かに特化するのです。
- ジャンルで絞る:
- 食パン専門店
- あんぱん専門店
- カレーパン専門店
- 抹茶を使ったパン専門店
- クリームパン専門店(メシテロ系)
- ターゲットで絞る:
- アレルギー対応パン専門店(小麦、卵、乳製品不使用など)
- ヴィーガン向けパン専門店
- 筋トレ愛好家向け高タンパク・低糖質パン専門店
- 子供向けキャラクターパン専門店
- 地域で絞る:
- 「〇〇(地名)で一番のメロンパン専門店」
- 「△△駅前で唯一の早朝営業パン屋」
このように絞り込むことで、
- ライバルが少なくなる: 「食パン専門店」のライバルは他の食パン専門店であり、全てのパン屋さんではありません。
- 顧客にとっての魅力が増す: 「食パンが好きなら、あそこに行けば間違いない」という認識が生まれます。
- 専門性が高まる: 特定の分野にリソースを集中できるため、品質や独自性を高めやすくなります。
- 話題性が生まれる: 「〇〇専門」というだけで、メディアに取り上げられたり、口コミが広がりやすくなったりします。
事例:日本一痛いヘッドスパ? – 逆転の発想
以前、新宿でヘッドスパ店の立ち上げに関わったことがあります。
ヘッドスパ市場もまた、競争の激しいレッドオーシャンでした。
多くの店が「気持ちよさ」「リラクゼーション」「寝落ち体験」を売りにしています。
そこで考えたのは、真逆のコンセプトです。
「気持ちよくて寝てしまう」のではなく、「施術はめちゃくちゃ痛い。でも、終わった後の効果は絶大」というコンセプト。
- ターゲット: 本当に肩こりや頭痛に悩んでいて、根本的な改善を求めている人。
- 提供価値: 強い刺激で血行を促進し、施術後の爽快感と深い睡眠を提供する。
- コンセプト: 「日本一痛いヘッドスパ(でも、効果は本物)」
この尖ったコンセプトが話題を呼び、多くのメディアに取り上げられました。
「気持ちよさ」を求める顧客は来ませんが、「本気で改善したい」という顧客が殺到し、結果的に地域で圧倒的な人気店となったのです。施術内容もシンプルなので、スタッフの育成も容易でした。
このように、ライバルとは違う土俵(コンセプト)を作り出すことが、競争を勝ち抜く鍵となります。
絞り込みの注意点 – 求められていないものは響かない
「絞り込めば何でもいいのか?」というと、そうではありません。
コンセプトメイキングで最も重要な注意点があります。
それは、「そのコンセプト(絞り込んだもの)を、市場(顧客)は求めているか?」ということです。
市場とは、「問題や悩みを感じている人の数」であると捉えることができます。
どんなにユニークで、どんなに専門的なコンセプトを打ち出しても、それを求める人、その悩みを抱えている人がいなければ、ビジネスとして成り立ちません。
先ほどのパン屋の例で言えば、「納豆とカレーとコーヒー豆を混ぜた、世界で唯一のパン」を作ったとしても、それを食べたいと思う人は、おそらくほとんどいないでしょう。これは極端な例ですが、独りよがりな絞り込みは失敗のもとだということです。
コンセプトを考える際には、必ず以下の視点を持ってください。
市場(顧客)には、どんな問題や悩み、欲求が存在するのか?
その中で、まだ十分に満たされていないものは何か?
自分たちは、どの問題解決や欲求充足に特化できるか?
市場のニーズを的確に捉え、その上で「求められている絞り込み」を行うこと。
これが、成功するコンセプトメイキングの要諦です。
2. コンテンツメイキング: 期待を超える価値の創造
コンセプトが決まり、ビジネスの方向性が定まりました。
次に創造すべきは、そのコンセプトを具体的に形にする「中身」、すなわち「コンテンツ(商品・サービス)」です。
「良い商品を作れば、顧客は満足し、リピーターになってくれる」
これは、多くの人が直感的に理解できることでしょう。
では、「良い商品・サービス」とは、具体的に何を指すのでしょうか?
「美味しさ」?「機能性」?「デザイン」?
もちろん、それらも重要な要素です。
しかし、顧客が「良い」と感じるかどうかを最終的に決定づける、もっと本質的な定義があります。
それは、
顧客の「期待」よりも、「実際」が上回っていること
です。
つまり、「期待値」と「実際の体験」との間に、ポジティブな「ギャップ」があるかどうか。
映画の例を思い出してください。
大ヒットしたアニメ映画「君の名は。」。多くの人が、公開前の予告編を見て、「男女が入れ替わる、よくあるラブコメかな?」といった程度の期待感を持っていたかもしれません。
しかし、実際に映画館で観てみると、予想を遥かに超える壮大なストーリー、美しい映像、感動的な音楽に心を揺さぶられました。
この「期待と現実の大きなギャップ」こそが、多くの人に「この映画は素晴らしい!」と感じさせ、記録的なヒットに繋がった大きな要因の一つです。
逆に、どんなに評判の良いレストランでも、「絶対に美味しいはずだ!」と過剰な期待を持って訪れると、たとえ料理が美味しくても、「まあ、こんなものか」と、感動が薄れてしまうことがあります。
これは、全てのビジネスに共通して言えることです。
顧客が「良い」と感じるのは、絶対的な品質だけではありません。その商品やサービスに触れる前に抱いていた「期待値」を、実際の体験がどれだけ上回ったかによって、満足度や感動の度合いは大きく左右されるのです。
であるならば、コンテンツメイキングにおいて重要になるのは、単に品質を高めることだけではありません。
顧客の「期待値」を、いかにコントロールするか
という視点が不可欠になります。
これを「期待値コントロール」と呼びます。
- 過剰な期待を煽らない: 「最高」「完璧」といった言葉でハードルを上げすぎると、少しの欠点でも顧客をがっかりさせてしまう可能性があります。
- 適切な期待感を醸成する: 商品やサービスの本当の価値や特徴を、誠実に、しかし魅力的に伝えることで、適切な期待値を設定します。
- サプライズを用意する: 期待していなかった小さな配慮や、予想外の付加価値を提供することで、ポジティブなギャップを生み出し、感動を与えることができます。(例:レストランでの記念日プレート、購入後の丁寧なフォローアップなど)
もちろん、大前提として、提供するコンテンツ(商品・サービス)そのものの質を高める努力は必要です。期待値コントロールは、その上でさらに顧客満足度を高めるための、上級テクニックと言えるでしょう。
初心者のうちは、まず「顧客が期待している以上のものを提供する」ことをシンプルに目指しましょう。
顧客が何を期待しているのかを理解し、それを少しでも上回る努力を続けること。それが、ファンを作り、リピーターを増やすための確実な一歩となります。
3. リストメイキング: 継続的な「関係性」の創造
コンセプト(概念)を作り、コンテンツ(中身)を創造しました。
次に取り組むべきは、「リストメイキング」、すなわち顧客との継続的な「関係性」を創造し、維持していくことです。
このリストメイキングの基本的な考え方については、既に「DRM(ダイレクトレスポンスマーケティング)」と「回遊」のセクションで触れました。
- DRMの基本: 見込み客の連絡先(リスト)を獲得し、教育(信頼構築)を経て、販売へと繋げる。
- 現代の課題: リストを集めても忘れられたり、反応が鈍くなったりする(リスト毀損)。
- 回遊の重要性: メールやLINEだけでなく、SNSなど複数の接点を持ち、顧客を常に自社の周りで泳がせ続けることで、忘れられない存在になる。
リストメイキングとは、単にメールアドレスやLINEの友だちを集めることではありません。それは、あくまで関係性を始めるための「きっかけ」に過ぎません。
真のリストメイキングとは、
獲得したリスト(見込み客・顧客)との間に、長期的で良好な関係性を築き、維持していくための仕組み全体
を指します。
それは、
- 定期的なメールマガジンによる価値提供かもしれないし、
- SNSでの日々のコミュニケーションかもしれないし、
- 購入者限定のコミュニティ運営かもしれないし、
- 顧客一人ひとりに合わせた個別のアプローチかもしれません。
重要なのは、「売りたい時だけ連絡する」のではなく、常に顧客にとって価値のある情報や、心地よいコミュニケーションを提供し続けることです。
「この人(会社)の情報は役に立つな」
「いつも気にかけてくれているな」
「なんだか応援したくなるな」
顧客にそう感じてもらうことで、リストは単なる連絡先の集まりではなく、信頼と共感で結ばれた「コミュニティ」へと変化していきます。
そうなれば、新商品を発売したとき、イベントを開催したとき、あるいは何か協力を呼びかけたとき、顧客は喜んで反応してくれるでしょう。
リストメイキングは、短期的な売上を追うのではなく、長期的な視点で顧客との関係性を育む、地道ながらも極めて重要な活動なのです。
最初のコンセプトメイキング、コンテンツメイキングで築いた価値を、このリストメイキングを通じて、継続的に顧客へと届け、深めていく。それが、持続的なビジネス成長の鍵となります。
4. メディアメイキング: 広範な「認知」の創造
コンセプト、コンテンツ、リストという、マーケティングの土台となる最初の3つのメイキングが固まってきたら、次に視野に入れるべきが「メディアメイキング」です。
メディアメイキングとは、文字通り、「メディア(媒体)」を活用して、より広範囲な「認知」を獲得し、ブランドイメージを構築していく活動を指します。
主な目的は以下の2つです。
- 認知度の向上: より多くの人々に、あなた(のビジネス、商品、サービス)を知ってもらうこと。
- ブランディング: 顧客の心の中に、特定の好ましいイメージ(ブランド)を築き上げること。
これは、先の3つのメイキングがある程度機能し、ビジネスが軌道に乗ってきた中級以上の段階で、さらにスケールアップを目指す際に重要になってきます。
どのようなメディアを活用するのでしょうか?
- マスメディア: テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など。広範囲なリーチと高い信頼性が期待できますが、コストも高くなります。
- ウェブメディア: ニュースサイト、専門メディア、インフルエンサーのブログなど。ターゲットを絞った情報発信や、深い情報提供が可能です。
- SNS: (リストメイキングの「回遊」とも重なりますが)広告出稿やインフルエンサーとの連携などを通じて、より戦略的に認知度を高めることができます。
- 書籍出版: 専門性や権威性を示し、ブランドイメージを高める効果があります。
- イベント登壇: 業界内での認知度を高め、直接的な見込み客獲得にも繋がります。
メディアメイキングで重要なのは、単に露出を増やすことではありません。
「どのようなイメージで認知されたいか」というブランディング戦略と連動している必要があります。
ブランドとは何か?
ブランドとは、単なるロゴや名前ではありません。
それは、顧客の心の中に存在する、特定の企業や商品に対する「印象」や「感情」の総体です。
「スターバックスのコーヒーは、なぜ他のコーヒーショップより高くても多くの人に選ばれるのか?」
それは、単にコーヒーが美味しいからだけではありません。「おしゃれな空間」「洗練された体験」「自分へのご褒美」といった、スターバックスというブランドが持つ独自のイメージに、人々は価値を感じているからです。
ブランディングとは、「〇〇といえば、□□」という、顧客の心の中の特定のポジションを確立する活動です。
- 「高級感といえば、〇〇」
- 「信頼性といえば、△△」
- 「楽しさといえば、××」
この「選ばれる理由」を意図的に作り上げていくのがブランディングであり、メディアメイキングはそのための強力な手段となります。
どのようなメディアで、どのようなメッセージを発信すれば、理想とするブランドイメージを構築できるか?
これを戦略的に考え、実行していくのがメディアメイキングの核心です。
(※ブランディング戦略の詳細については、非常に奥が深いため、別の機会に譲りたいと思います。ここでは、メディアメイキングが認知度向上とブランディングのための活動である、という点を理解しておいてください。)
5. ルールメイキング: 有利な「環境」の創造
最後のメイキングは、「ルールメイキング」です。
これは、少し特殊な、しかし時には絶大な効果を発揮するアプローチです。
ルールメイキングとは、自分(自社)にとって有利な「ルール」や「環境」そのものを創り出してしまう、あるいは既存のルールを巧みに利用することで、マーケティングの力だけに頼らず、力技で状況を好転させる戦略を指します。
これまでの4つのメイキングが、市場の中で正攻法で戦うための戦略だとすれば、ルールメイキングは、その戦いの「土俵」自体に影響を与えるような、より高度な戦略と言えます。
分かりやすい例を挙げましょう。
あなたがイベントを企画し、3000人を集めたいと考えたとします。
しかし、あなたの現在の集客力では、頑張っても20人しか集められません。
コンセプト、コンテンツ、リスト、メディアを駆使しても、短期間で3000人を集めるのは至難の業です。
ここで、ルールメイキングの視点が活きてきます。
自分の力だけで集められないなら、他の人の力を借りればいいのではないか?
例えば、
- 既に3000人以上の顧客リストを持つ、影響力のある企業や個人と提携(ジョイントベンチャー)する。
- イベントの趣旨に賛同してくれるスポンサーを募り、そのスポンサーのネットワークを活用して集客する。
- 業界団体や行政機関などを巻き込み、公的なお墨付きを得ることで、集客力を高める。
このように、自分以外のリソース(人脈、資金、信頼性など)を上手く活用することで、自力では到底達成できないような目標を、一気にクリアできる可能性があります。
あるいは、
- 特定の業界標準や資格制度の設立に関与し、自社に有利なルールを作る。
- 法規制の変更を働きかけ、競合他社よりも有利なポジションを築く。
といった、より大きなスケールでのルールメイキングも存在します。(これは大企業や業界団体レベルの話になることが多いですが)
中小企業や個人事業主にとって、より現実的なルールメイキングは、「他者の力を借りる」という視点です。
「自分には人脈がない」「大手企業との繋がりがない」
そう感じるかもしれません。しかし、世の中には、そうした繋がりを仲介してくれる存在もいます。
- 顧問やコンサルタント: 豊富な人脈や交渉力を持つ専門家に依頼し、大手企業との提携などを仲介してもらう。
- ビジネスマッチングサービス: 自社のニーズに合った提携先を探してくれるプラットフォームを活用する。
これらのサービスを利用するにはコストがかかりますが、それによって得られるメリット(売上の飛躍的な向上、事業規模の拡大など)を考えれば、十分に価値のある投資となる場合があります。
ルールメイキングは、一見するとマーケティングの本流から外れているように見えるかもしれません。しかし、限られたリソースの中で最大限の成果を出すためには、時にはこのような「ゲームのルール」そのものを変える発想が、極めて有効な武器となるのです。
(※他者の力を借りる具体的な交渉術や提携の方法についても、非常に実践的なノウハウが必要となります。これもまた、別の機会に詳しく解説できればと思います。)
5つのメイキングのまとめ
- コンセプトメイキング: 勝てる土俵を見つける(市場、ライバル、専門性、絞り込み)
- コンテンツメイキング: 期待を超える価値を創造する(期待値コントロール)
- リストメイキング: 継続的な関係性を創造する(DRM、回遊、コミュニティ化)
- メディアメイキング: 広範な認知とブランドを創造する(メディア活用、ブランディング)
- ルールメイキング: 有利な環境を創造する(他者の力、提携、交渉)
この5つのステップを意識し、それぞれの段階で適切な戦略を実行していくこと。
それが、再現性高く売上を伸ばし、ビジネスを成長させていくための、マーケティングの王道と言えるでしょう。
特に、最初の3つ(コンセプト、コンテンツ、リスト)は、全てのビジネスの基礎となります。まずはここをしっかりと固めることから始めてください。
終章: あなたが今日からできること – マーケティング思考の第一歩
ここまで、マーケティングの本質から、具体的な構造、そして戦略の核心である「5つのメイキング」に至るまで、その全体像を駆け足で見てきました。
もしかしたら、情報量の多さに少し圧倒されているかもしれません。
「何から手をつければいいのだろう?」と感じているかもしれません。
それで良いのです。
一度読んだだけですべてを理解し、完璧に実行できる人はいません。
大切なのは、今日学んだことを、あなた自身の状況に置き換えて考え始めることです。
- コンセプト: あなたの商品やサービスは、顧客のどんな問題を解決し、どんな価値を提供していますか?ライバルとの違いは何ですか?もっと魅力的なコンセプトにできないでしょうか?
- コンテンツ: 顧客はあなたのコンテンツ(商品・サービス)に、どんな期待を寄せていますか?その期待を上回る体験を提供できていますか?
- リスト: あなたは、見込み客や顧客との継続的な関係性を築けていますか?彼らに忘れられないための工夫をしていますか?
- メディア: より多くの人に知ってもらうために、どんなメディアを活用できますか?どのようなブランドイメージを築きたいですか?
- ルール: あなたの力を何倍にもしてくれるような、外部のリソースや提携先はありませんか?
これらの問いに、すぐに完璧な答えを出す必要はありません。
まずは、考え始めること、問いを持つことが、マーケティング思考の第一歩です。
マーケティングとは、特別な才能を持つ人だけのものではありません。
それは、顧客を理解し、価値を届け、関係性を築くための、普遍的な思考プロセスです。
今日、この長い旅にお付き合いいただいたあなたが、マーケティングという名の霧の中から一歩踏み出し、自らの手で未来を切り拓いていくための一助となれたなら、これ以上の喜びはありません。